- ホーム
- ブログ
- 2019年1月
- 2019年2月
- 2019年3月
- 2019年4月
- 2019年5月
- 2019年6月
- 2019年7月
- 2019年8月
- 2019年9月
- 2019年10月
- 2019年11月
- 2019年12月
- 2020年1月
- 2020年2月
- 2020年3月
- 2020年5月
- 2020年6月
- 2020年7月
- 2020年8月
- 2020年9月
- 2020年10月
- 2021年1月
- 2021年2月
- 2021年3月
- 2021年4月
- 2021年5月
- 2021年6月
- 2021年7月
- 2021年8月
- 2021年9月
- 2021年10月
- 2021年11月
- 2021年12月
- 2022年1月
- 2022年2月
- 2022年3月
- 2022年4月
- 2022年5月
- 2022年6月
- 2022年7月
- 2022年8月
- 2022年9月
- 2022年10月
- 2022年11月
- 2022年12月
- 2023年1月
- 2023年2月
- 2023年3月
- 2023年4月
- 2023年5月
- 2023年6月
- 2023年7月
- 2023年8月
- 2023年9月
- 2023年10月
- 2023年11月
- 2023年12月
- 2024年1月
- 2024年2月
- 2024年3月
- 2024年4月
- 2024年5月
- 2024年6月
- 2024年4月
- 2024年5月
- 2024年6月
- 2024年7月
- 2024年8月
- 2024年9月
- 2024年10月
- 2024年11月
- 2024年12月
- 2025年1月
- 2025年2月
- 小野幌の一年
- 指導方針
- 入会案内
- お問い合わせ
- 会員専用
- 50年のあゆみ
小野幌の一年
4月
新年度スタート
5月
全道中学校剣道錬成会
開催地:当別町
通称「当別錬成会」と呼ばれ、連休中の2日間に開催される錬成会です。

赤胴大会及び全道中学校大会選考会
開催地:厚別区
8月に行われる「北海道少年剣道錬成大会及び赤胴大会」と、9月に行われる「北海道中学生剣道錬成大会」の出場権をかけた選考会です。
6月
前期級位審査 開催地:厚別区
道新杯少年剣道大会 開催地:小樽
7月
青少年剣道旭川大会 開催地:旭川

中体連剣道選手権 開催地:札幌市内
札幌市民スポーツ大会剣道競技会予選会
開催地:厚別区
8月
北海道少年剣道錬成大会 及び 赤胴少年剣道錬成大会
開催地:真駒内アイスアリーナ
全道から個人戦出場者が200名近く、団体チームも150を超える人数が参加します。小学生はこの大会を目標に稽古してきており、まさに晴れ舞台です。
9月
札幌市民スポーツ大会剣道競技会
開催地:美香保体育館
厚別区の代表として、個人戦と団体戦を戦います。

レク 開催地:札幌近隣
ここ近年は江別のえみくるで行っています。

北海道中学生剣道錬成大会
開催地:砂川
通称「砂川大会」と呼ばれています。
5月に行われた選考会を経て、厚別区選抜チームとして出場します。
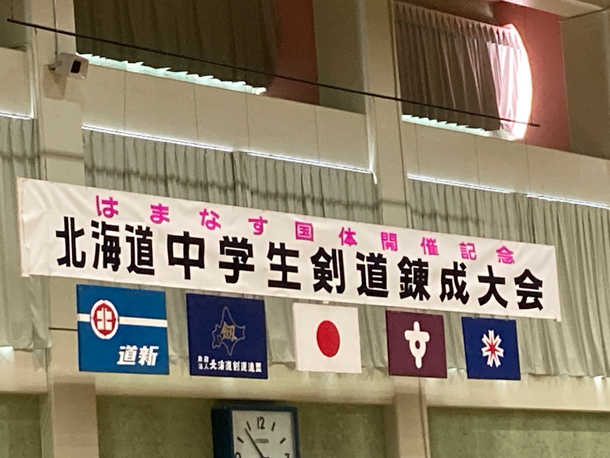
北海道神宮少年剣道大会
開催地:北海道神宮
北海道神宮の駐車場で行われ、靴を履いたまま試合を行います。

10月
札幌市スポーツ少年団剣道交流大会
開催地:札幌市内
個人戦は全道大会、全国大会につながる大きな大会です。各部門の入賞者は札幌代表として、全道、全国に向けて強化稽古に励みます。

段審査 開催地:札幌
出稽古
小学校の学習発表会のために体育館の使用ができないこの時期は、近隣の体育館を借りたり、兄弟剣道会の上野幌剣道会に出稽古に行ったりします。
11月
中体連新人戦 開催地:札幌市内
毎年、11月3日に行われ、中学校1、2年生がそれぞれの学校の代表として出場します。
12月
当別ちびっこ錬成会 開催地:当別町
剣道を始めたばかりの小さい子供たちでも出場できる大会です。

厚別区青少年武道大会 開催地:厚別区
稽古納め
1月
鏡開き

後期級位審査会 開催地:厚別区
2月
豆まき

札幌市スポーツ少年団剣道交流戦新人戦
開催地:札幌市内
3月
厚別区剣道祭 開催地:厚別区
納会大会
この納会をもって、中学3年生は小野幌剣道会を卒団します。みんなで食事をし卒団生を祝います。
